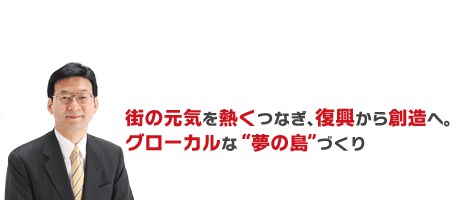那覇市の「第一牧志公設市場」、うるま市の「公共交通空白地域の解消に向けた取り組みについて」、「うるマルシェ」を会派視察しました。
 4月14日㈪、会派視察で福島駅を朝6時45分発で那覇市へ向かい、午後3時過ぎに「第一牧志公設市場」入り口で那覇市役所の担当の方と待ち合わせをし、3階の多目的室で説明・質疑をいただいた後、1階の公設市場を案内いただきました(写真①)。
4月14日㈪、会派視察で福島駅を朝6時45分発で那覇市へ向かい、午後3時過ぎに「第一牧志公設市場」入り口で那覇市役所の担当の方と待ち合わせをし、3階の多目的室で説明・質疑をいただいた後、1階の公設市場を案内いただきました(写真①)。
施設は1階が小売店舗、2階が飲食店、3階が調理体験室・多目的室等で構成され、精肉12・鮮魚16・生鮮23・外小間24・食堂12の87店舗が営業しています。
令和4年に竣工・供用開始された第一牧志公設市場整備事業(沖縄の食の魅力発信整備事業)の基本方針は、①沖縄の食文化を継承・発展する市場づくり②観光地としての魅力向上に寄与する市場づくりでした。中心市街地の中心として回遊性の向上と集客力を高め、中心市街地への来訪者、観光客の拡充を目的としています。また、1972年の改築から約半世紀が経ち、建物や設備の老朽化の進行、来場者の安全確保、衛生環境の改善など再整備を急ぐ必要があったと言います。
新市場建設工事の再整備では、近くにあった「にぎわい広場」にプレハブ店舗を整備して市場機能を移転させ、仮店舗にて営業したとのこと。データとして、市場の1日当たりの平均入客数は約5000人弱で、その内訳は地元客12%、日本人観光客69%、外国人観光客19%です。
 4月15日㈫は、午前中に那覇市からうるま市へ琉球バス交通の路線バスで約80分かけて移動しました。「沖縄県はマイカー移動がほとんどで公共交通は約1%」(都市政策課)という現状を実感させられました。
4月15日㈫は、午前中に那覇市からうるま市へ琉球バス交通の路線バスで約80分かけて移動しました。「沖縄県はマイカー移動がほとんどで公共交通は約1%」(都市政策課)という現状を実感させられました。
午後一で、うるま市役所で都市政策課の皆さんに「公共交通空白地域の解消に向けた取り組みについて」視察を行いました。
うるま市は、平成17年4月1日、旧具志川市、旧石川市、旧勝連町、旧与那城町の2市2町が合併して誕生し、合併当初11万5千人の人口は、令和4年4月1日時点では12万5千人と、少しずつ増加傾向にあります。
うるま市は東西と南北に長い地形・島しょ地域の特色を捉えた「多極連携・集約型都市」の形成を目指す中で、「合併したものの足がない」という課題克服に向けて、この間、市で取組んできたデマンド交通実証運行や公共施設間連絡バス取組等について説明(写真②)をいただきました。
令和3年度事業で取り組んだデマンド交通実証運行は、「ドアtoドアへの根強いニーズ」、「利用登録の手間」、「他の方との乗合を避ける傾向」といった理由から、利用が大幅に想定を下回る結果に。一方、公共施設間連絡バス取組は令和3年度から継続中で、4路線で利用者数も令和6年度は年間32,674人ということです。バス乗車運賃は無料で、市がバスを所有して運転手費用・燃料費も持ち、運営はシルバー人材センターに委託しています。担当課としては「令和5年度にはコミュニティバス(有償)への移行を検討していたが、その後見送りになった経緯があり、その場合はバス会社への委託を考えていたといいます。


同日(4月15日の)夕方、「うるマルシェ(うるま市農水産業振興戦略拠点施設)」を視察しました(写真③)。説明いただいたのは、指定管理者の株式会社ファーマーズ・フォレストで、道の駅ふくしまでもお世話になっています。
今回は、うるマルシェ統括支配人の宮城健さんに、2018年オープン以来の取り組みと店内の案内をしていただきました。特に、「地域商社」として地域活性化につながる様々な取り組みを紹介いただき、参考になる有意義な時間でした。
訪れて、最初に感じたのは立地です。周辺にイオン具志川店やドラッグストア、外食店などの競合他社が立ち並ぶ郊外の激戦エリアでした。差別化のコンセプト等が明確でないと、生き残ることが厳しいところと感じました。
基本理念は、「『食』を通じてうるま市を元気にする~うるま市経済成長のエンジン~」。5つの基本方針は、①やりがいと収入が連動し、次世代が積極的に参入する農水産業の実現。②農水産業の6次化推進とブランド力強化による、うるま市産業の活性化。③農水産業による賑わいと地域コミュニティの創出。④豊富な農産物を生かした観光客の誘客と周辺観光との連動。⑤地元農産物の魅力を集積し、スケールメリットを生かした地産地消の推進、です。
地元商社の取り組みでは、うるま市農水産業振興戦略拠点施設として、地域の生産者や事業者は登録1200名の中で実動400名。市内半分・市外18%、地元の食を支えるので仕入れ商品も並んでいるといいます。ターゲット設定では、90%が地元客で、10%が観光客です。直売所の手数料は15%と低く抑えているため、「質の高いサービス」よりも「お客さんが欲しがるものを集める」方針とか。
地域活性化につながる取り組みもこれまで様々挑戦。①地域の特産品ブランド構築と過疎対策事業、②ブランド芋構築と黄金芋生産者の応援、③ブランド豚の構築、養豚生産者の応援、④ブランド牛の構築と肉牛生産者の応援、⑤多彩な地元農産物イベント、⑥旬の地元農産物のキッチンスクールなどを開催。「うるマルシュを地元みんなの施設として可愛がってもらわないと」と、統括支配人の宮城健さんが話されました。後日、目にしたPR誌「マルシェレター」(写真④)でも、「地域の皆様に愛される永続的な施設に」と語り、強い思いが伝わってきました。
翌4月16日㈬。うるま市の隣の沖縄市から、まず路線バスで那覇市へ戻り、羽田空港、福島市へ帰りました。かなりの強行軍で腰に不安を抱えたまま、視察を乗り切ることができ、正直ホッとしました。