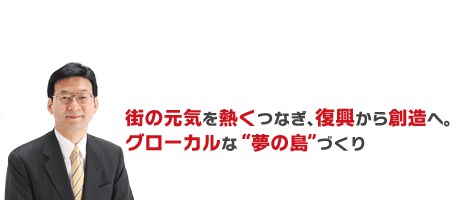福島県チャイルドライン啓発フォーラム「聴いていますか子供の声」に参加しました。「個性や失敗に寛容な世の中であったら、子どもはもっと生き易くなるのではないでしょうか…」と倉持氏。
 3月22日㈯は午後から、コラッセふくしま多目的ホールで開催された福島県チャイルドライン啓発フォーラム「聴いていますか子供の声」に参加しました。
3月22日㈯は午後から、コラッセふくしま多目的ホールで開催された福島県チャイルドライン啓発フォーラム「聴いていますか子供の声」に参加しました。
基調講演は、「子どもの権利条約について考える~こどもの主体性を育むために~」をテーマに、倉持惠氏(雪うさぎ法律事務所・弁護士)が基調講演、続いて「子どもは社会を共につくるパートナー」をテーマにトークセッションがあり、登壇者は青葉学園の神戸信之氏、こおりやま子ども若者ネットワーク副代表の大岡桂子氏で、福島県チャイルドライン推進協議会理事長の野口まゆみ氏をコーディネーターに、倉持惠氏がアドバイザーを務めました。
まず、基調講演では、基本的な学び直しがありました。子どもの権利条約は、19889年11月20日に国連総会で採択され、締約国・地域は196で、世界で最も受け入れられている人権条約です。1994年に日本も批准して、国内法として効力をもち、憲法の次に優先される国内法規となりました。憲法≫条約≫法律≫条令の順です。いくつかの気づかされた点をメモ書きしました。
①2条・差別の禁止の中で、「本人だけでなく、親の地位、活動、思想信条などを理由にする差別も禁止。」
②12条・の子供の意見の尊重では、日本では不十分で自己決定能力が十分に育たず、交渉能力が育たない中で大人になってから「カスハラ」を生んでいる。
③28条、29条・教育を受ける権利では、「教育それ自体が人権+他の人権を実現する不可欠な手段」であること。
④31条・休み、遊ぶ権利・「残念ながら遊ぶ権利を保障するような法律や制度は(日本には)ない。そこまで達していない。」
倉持氏の講演の最後に、子どもの主体性を育むために、「もう少し広い目で」必要なこととして、「子どもコミッショナー(子どもオンブズパーソン、子ども人権救済機関)」について説明。子ども基本法ができたときに見送られたが、国内では数十の自治体に存在しています。なぜ必要かと言えば、裁判では解決できない問題がたくさんあり、第三者委員会は学校のいじめや死亡事故しか機能していないからと、今後の課題を提起されました。
後半のトークセッションでは、チャイルドラインに寄せられた「つぶやき」を中心に進められました。つぶやきは、「もっと生きたいという叫び声」と大岡桂子氏。神戸信之氏の話に出た「失敗」から倉持惠氏は「失敗する権利がそもそもあるのでは」とつなぎました。
「今の日本は失敗を許さない。これが子供を生きづらくして苦しめている。子どもの個性や失敗に寛容な世の中であったら、生き易くなるのではないでしょうか…」と倉持氏。もう少し失敗も一つの経験として、許容する社会になれれば、子どもも大人も伸び伸びと生き易くなりそうですね。