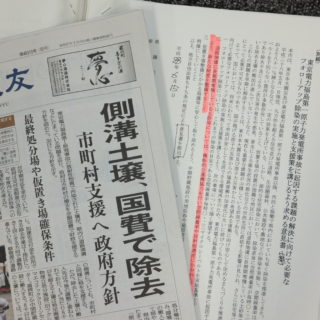大学のゼミの恩師が「2019ふくしま平和のための戦争展」で講演を

大学のゼミの恩師、星埜敦(あつし)先生が91歳の体を押して「2019ふくしま平和のための戦争展」で講演をされるとゼミの先輩から聞いて、8月14日午後からはコラッセへ。演題は、「原爆投下の『時』を生きて」でした。
広島に原爆が投下された8月6日は、当時の星埜青年は広島高等学校の寮生でした。「寮長から先生の呉の自宅へ食料をもらいに行ってくれと頼まれ、朝7時45分に広島駅で仲間の寮生と別れました。(そして、原爆投下のその時、)呉に向かう列車の鎧戸のすき間から青い光が左目に入りました(後に発症)。呉から見ると、広島方面にピンクがかった薄墨色の雲があり、不吉な予感がした」と。
広島に戻ると、幸い寮の建物は残り、寮生の救援活動を開始する。しかし、薬は唯一あったのが「ごま油と赤チン」。治療はするが、被爆した仲間の寮生の体からは手に負えないほどの蛆虫が次から次へと湧いて出て、その中でやがて息を引き取ります。
最終的に寮に集められた被爆者、その中で「亡くなった多くの方々は毛布ごと、庭に掘った穴に投げ込み、重油をかけて焼きました」。この作業を2週間ぐらい続けたといいます。やがて、高校が閉鎖されて、先生は呉の自宅に帰ります。先生自身が2次被爆していたため、8月25,6日頃に倒れ、意識不明で2週間ほど寝込んでいたといいます。
この日の話が終わり、会場に集まった若者の質問に応えて、「(原爆投下後の地獄絵的な中で懸命の救助活動をする内、)だんだんに感情が動かなくなり、非人間的になる。人間でなくなる。しばらく感情のない人間になってしまう。何を見ても感動しない。そういう状況に追い込まれた。長い間、回復するまで10年以上かかりました。おそらく、被爆者で戦争を肯定する者は一人もいない。完全に戦争に対しては否定的な考えを持っています」
原爆投下直後の救助活動にあたる中で、自ら「2号の被爆者」となりながら広島と向き合ってこられた恩師の姿は、40年前のゼミ生の時には感じることができませんでした。あの時の自分は、酒の勢いを借りながら青春特有の出口のないような悩みを先生に聞いていただくだけで、今にしてみれば恥ずかしさを感じるところです。